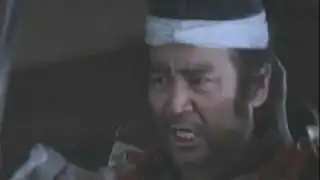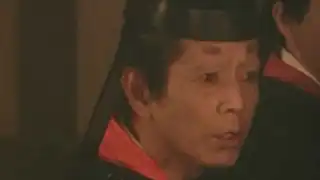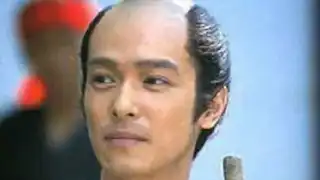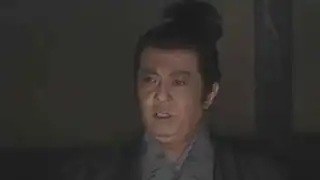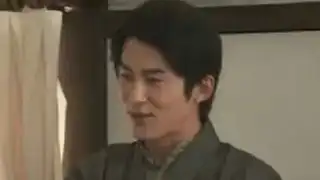偉人
偉人細川頼春
ほそかわ よりはる(1304-1352)
登場回数:1作
細川 頼春(ほそかわ よりはる)は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての武将、守護大名。室町幕府侍所頭人。阿波国・伊予国・備後国・日向国・越前国守護。通称は蔵人。官位は従四位下・讃岐守、刑部大輔。名門細川氏の一門で、のちに代々室町幕府管領職を世襲する嫡流細川京兆家の祖。
登場回数:1作
細川 頼春(ほそかわ よりはる)は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての武将、守護大名。室町幕府侍所頭人。阿波国・伊予国・備後国・日向国・越前国守護。通称は蔵人。官位は従四位下・讃岐守、刑部大輔。名門細川氏の一門で、のちに代々室町幕府管領職を世襲する嫡流細川京兆家の祖。