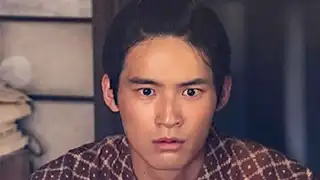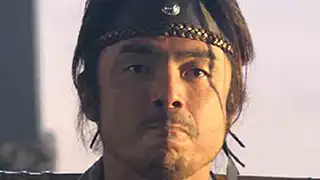偉人
偉人斯波義廉
しば よしかど(1445-?)
登場回数:1作
斯波 義廉(しば よしかど)は、室町時代中期から後期の武将、守護大名。室町幕府管領及び越前・尾張・遠江守護。足利氏一門の渋川氏出身で、父は渋川義鏡、母は山名宗全の伯父山名摂津守(実名不詳)の娘とされている。三管領筆頭の斯波氏(武衛家)を相続した(11代当主)。
登場回数:1作
斯波 義廉(しば よしかど)は、室町時代中期から後期の武将、守護大名。室町幕府管領及び越前・尾張・遠江守護。足利氏一門の渋川氏出身で、父は渋川義鏡、母は山名宗全の伯父山名摂津守(実名不詳)の娘とされている。三管領筆頭の斯波氏(武衛家)を相続した(11代当主)。