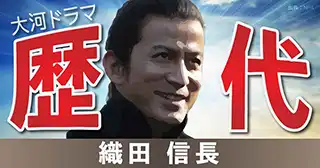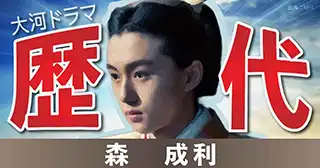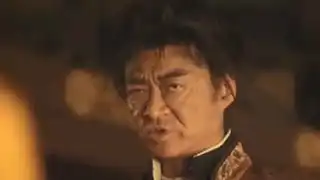偉人
偉人織田幹雄
おだ みきお(1905-1998)
登場回数:1作
織田 幹雄(おだ みきお、1905年(明治38年)3月30日 - 1998年(平成10年)12月2日)は、日本の陸上選手、指導者。広島県安芸郡海田町出身。1928年アムステルダムオリンピック三段跳金メダリスト。
登場回数:1作
織田 幹雄(おだ みきお、1905年(明治38年)3月30日 - 1998年(平成10年)12月2日)は、日本の陸上選手、指導者。広島県安芸郡海田町出身。1928年アムステルダムオリンピック三段跳金メダリスト。