寺内正毅
てらうち まさたけ(1852-1919)
登場回数:1作
寺内 正毅(てらうち まさたけ、旧字体:寺內 正毅、1852年2月24日〈嘉永5年2月5日〉- 1919年〈大正8年〉11月3日)は、明治・大正期の日本の陸軍軍人、政治家。軍人としての階級は元帥陸軍大将。位階は従一位。勲等は大勲位。功級は功一級。爵位は伯爵。 書の雅号は桜圃、魯庵。「ビリケン宰相」の異名を持つ。 陸軍大臣(第7代)、外務大臣臨時兼任(第2次桂内閣・寺内内閣)、韓国統監(第3代)、朝鮮総督(初代)、内閣総理大臣(第18代)、大蔵大臣(第19代)などを歴任した。 明治から大正にかけて陸軍軍人として活躍し、第1次桂内閣では児玉源太郎の後任として陸軍大臣に就任した。以来、第1次西園寺内閣や第2次桂内閣でも陸軍大臣を務めた。その後、曾禰荒助の後任として韓国統監に就任し、日本への併合を推し進めた。韓国併合後は朝鮮総督に就任した。のちに内地に帰還すると、寺内内閣を発足させ、内閣総理大臣を務めるとともに、外務大臣や大蔵大臣といった国務大臣を兼任した。元帥府に列せられていることから、階級を呼称する際には元帥の称号を冠して「元帥陸軍大将」と称される。
 偉人
偉人 偉人
偉人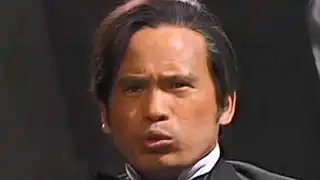 偉人
偉人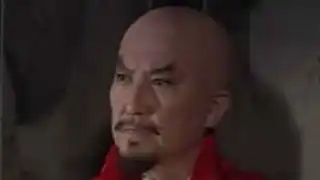 偉人
偉人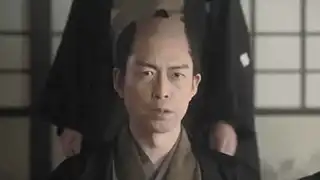 偉人
偉人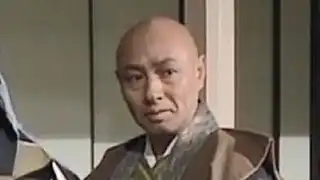 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人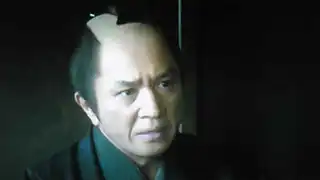 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人