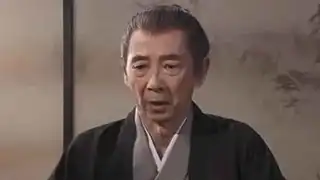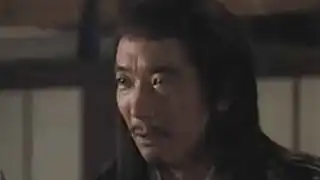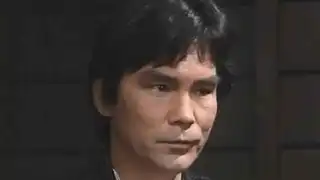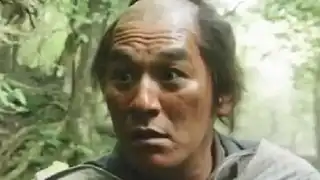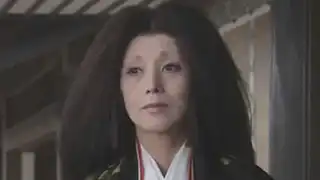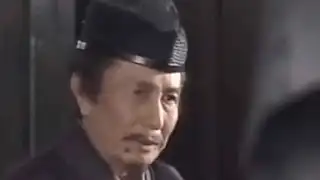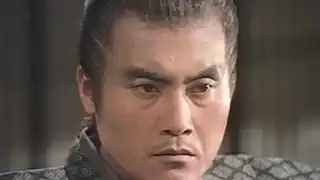 偉人
偉人原田宗輔
はらだ むねすけ(1619-1671)
登場回数:1作
別名:原田甲斐
原田 宗輔(はらだ むねすけ、元和5年(1619年) - 寛文11年3月27日(1671年5月6日))は、江戸時代前期の武士。仙台藩重臣。奉行職。原田宗資の子。伊達騒動(寛文事件とも)当事者の一人。通称は甲斐で、原田甲斐(はらだ かい)として知られる。
登場回数:1作
別名:原田甲斐
原田 宗輔(はらだ むねすけ、元和5年(1619年) - 寛文11年3月27日(1671年5月6日))は、江戸時代前期の武士。仙台藩重臣。奉行職。原田宗資の子。伊達騒動(寛文事件とも)当事者の一人。通称は甲斐で、原田甲斐(はらだ かい)として知られる。