 偉人
偉人相楽総三
さがら そうぞう(1839-1868)
登場回数:1作
相楽 総三(さがら そうぞう、天保10年(1839年) - 慶応4年3月3日(1868年3月26日))は、江戸時代末期(幕末)の尊皇攘夷派志士。江戸出身。赤報隊隊長。
登場回数:1作
相楽 総三(さがら そうぞう、天保10年(1839年) - 慶応4年3月3日(1868年3月26日))は、江戸時代末期(幕末)の尊皇攘夷派志士。江戸出身。赤報隊隊長。
 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人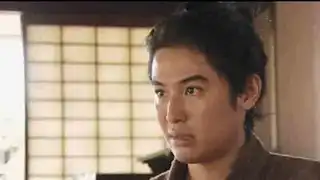 偉人
偉人 偉人
偉人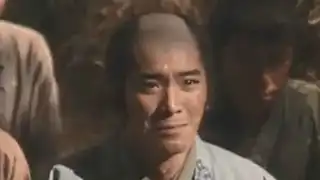 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人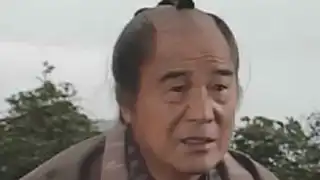 偉人
偉人 偉人
偉人