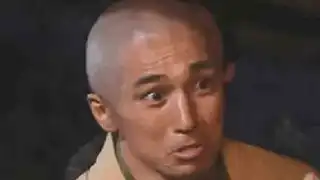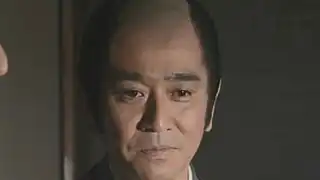偉人
偉人王士禎
おう してい(1634-1711)
登場回数:1作
王 士禎(おう してい、1634年10月19日(崇禎7年閏8月28日) - 1711年6月26日(康熙50年5月11日))は、中国清代初期の文人・詩人。字は貽上。号は阮亭・漁洋山人。諡は文簡。済南府新城県の出身。本来は「士禛(ししん)」の名であったが、死後、雍正帝が即位するとその諱「胤禛」を避けて「士正」と改名される。のち、乾隆帝の治世に「士禎」の名を賜った。号を以て「王漁洋」と称されることも多い。
登場回数:1作
王 士禎(おう してい、1634年10月19日(崇禎7年閏8月28日) - 1711年6月26日(康熙50年5月11日))は、中国清代初期の文人・詩人。字は貽上。号は阮亭・漁洋山人。諡は文簡。済南府新城県の出身。本来は「士禛(ししん)」の名であったが、死後、雍正帝が即位するとその諱「胤禛」を避けて「士正」と改名される。のち、乾隆帝の治世に「士禎」の名を賜った。号を以て「王漁洋」と称されることも多い。