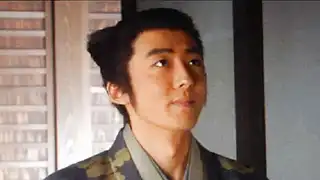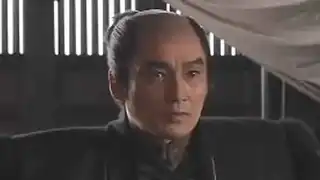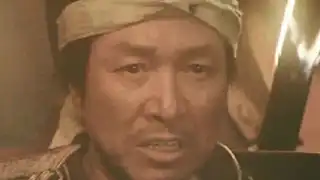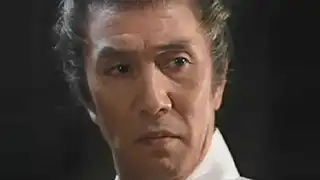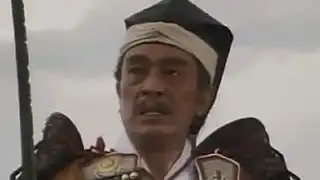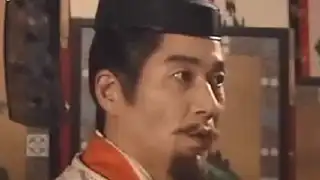偉人
偉人金森通倫
かなもり みちとも(1857-1945)
登場回数:1作
金森 通倫(かなもり みちとも、「つうりん」とも 安政4年8月15日〈1857年10月2日〉 - 昭和20年〈1945年〉3月4日)は、日本の宗教家・牧師。別名はポール・カナモリ。晩年は湘南の嶺山に隠居、原始的な洞窟生活をして「今仙人」といわれた。 政治家の石破茂は曾孫にあたる。
登場回数:1作
金森 通倫(かなもり みちとも、「つうりん」とも 安政4年8月15日〈1857年10月2日〉 - 昭和20年〈1945年〉3月4日)は、日本の宗教家・牧師。別名はポール・カナモリ。晩年は湘南の嶺山に隠居、原始的な洞窟生活をして「今仙人」といわれた。 政治家の石破茂は曾孫にあたる。