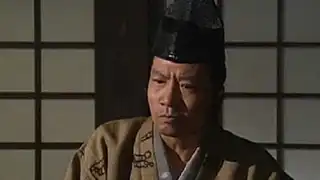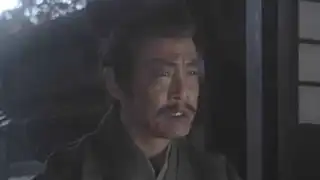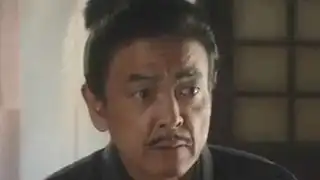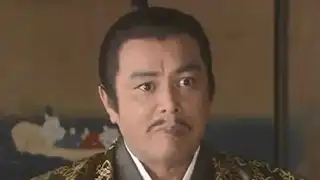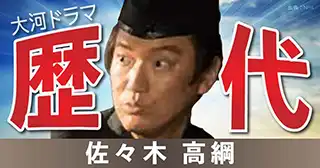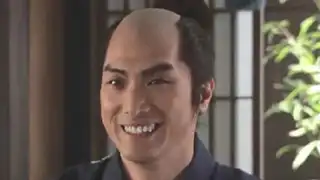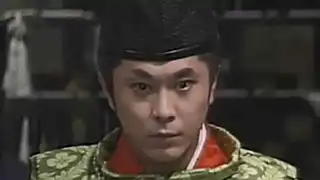 偉人
偉人護良親王
もりよししんのう(1308-1335)
登場回数:1作
護良親王(もりよししんのう)は、鎌倉時代末期から建武の新政期の皇族・僧侶・武将・天台座主・征夷大将軍。還俗前の名は尊雲法親王(そんうんほっしんのう)、通称を大塔宮(正式には「おおとうのみや」/俗に「だいとうのみや」)とも。一般に後醍醐天皇の第三皇子とされるが、一宮(第一皇子)という説もある。母は民部卿三位で、北畠師親の娘の資子という説と、勘解由小路経光(広橋経光)の娘の経子という説がある。尊珍法親王の異父弟。興良親王の父。 元弘の乱で鎌倉幕府を打倒することに主たる功績を挙げ、建武の新政では征夷大将軍に補任。しかし、尊氏を疎む護良は、武士好きで足利尊氏を寵愛した父とはすれ違いが多く、将軍を解任され、やがて政治的地位も失脚、鎌倉に幽閉される。のち、中先代の乱の混乱の中で、足利直義の命を受けた淵辺義博によって殺害された。鎌倉宮の主祭神。
登場回数:1作
護良親王(もりよししんのう)は、鎌倉時代末期から建武の新政期の皇族・僧侶・武将・天台座主・征夷大将軍。還俗前の名は尊雲法親王(そんうんほっしんのう)、通称を大塔宮(正式には「おおとうのみや」/俗に「だいとうのみや」)とも。一般に後醍醐天皇の第三皇子とされるが、一宮(第一皇子)という説もある。母は民部卿三位で、北畠師親の娘の資子という説と、勘解由小路経光(広橋経光)の娘の経子という説がある。尊珍法親王の異父弟。興良親王の父。 元弘の乱で鎌倉幕府を打倒することに主たる功績を挙げ、建武の新政では征夷大将軍に補任。しかし、尊氏を疎む護良は、武士好きで足利尊氏を寵愛した父とはすれ違いが多く、将軍を解任され、やがて政治的地位も失脚、鎌倉に幽閉される。のち、中先代の乱の混乱の中で、足利直義の命を受けた淵辺義博によって殺害された。鎌倉宮の主祭神。