レオポルド2世
れおぽるど2せい(1835-1909)
登場回数:1作
レオポルド2世(フランス語: Léopold II、1835年4月9日 - 1909年12月17日)は、第2代ベルギー国王(在位:1865年 - 1909年)。 初代ベルギー国王レオポルド1世の王太子として生まれ、1865年に父王の崩御に伴い即位。レオポルド2世の在位中、1884年までは自由党、それ以降はカトリック党が政権を担当していた。ベルギー経済は父王の代から引き続いて急速に成長を遂げたが、労働者階級の社会不安も増加。在位後半にはベルギー労働党が台頭したことで様々な社会改革が行われた。 即位前から植民地獲得に強い関心を持ち、他の列強の支配が及んでいないコンゴに目を付け、コンゴ国際協会を創設して探検を支援。先住民の部族長と協定を結ぶなどコンゴ支配の既成事実化を進めた。その結果、1884年のベルリン会議にてコンゴを私有地として統治することを列強から認められた(コンゴ自由国)。 コンゴにおける治世の初期は、鉄道敷設やアラブ人奴隷商人による奴隷狩りから黒人を守るなど、コンゴの近代化に努める面もあったが、先住民を酷使して天然ゴムの生産増を図り、イギリスなどから先住民に対する残虐行為を批判され、1908年にはコンゴをベルギー国家へ委譲することを余儀なくされた(王の私領からベルギー植民地への転換)。 1909年に崩御。嫡出子の男子がなく、甥のアルベール1世が王位を継いだ。
 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人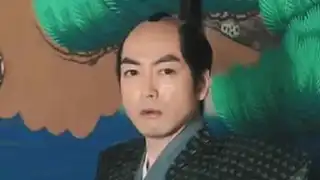 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人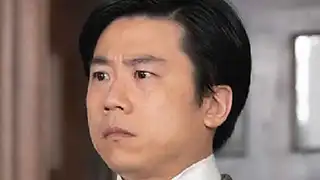 偉人
偉人 偉人
偉人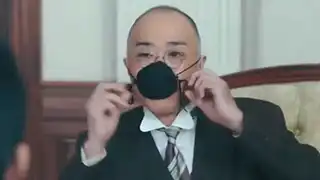 偉人
偉人 偉人
偉人