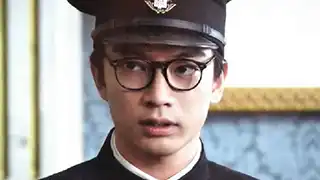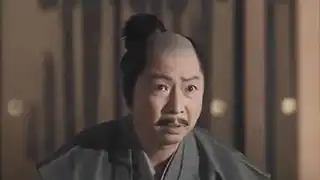偉人
偉人真竜院
しんりゅういん(1550-1647)
登場回数:1作
別名:真理姫
真竜院(眞龍院、しんりゅういん、天文19年(1550年) - 正保4年7月7日(1647年8月7日))は、戦国時代から江戸時代初期にかけての女性。武田信玄の三女で、木曾義昌の正室。俗名は真理姫(まりひめ)と伝わる。兄に武田義信、武田勝頼がいる。
登場回数:1作
別名:真理姫
真竜院(眞龍院、しんりゅういん、天文19年(1550年) - 正保4年7月7日(1647年8月7日))は、戦国時代から江戸時代初期にかけての女性。武田信玄の三女で、木曾義昌の正室。俗名は真理姫(まりひめ)と伝わる。兄に武田義信、武田勝頼がいる。