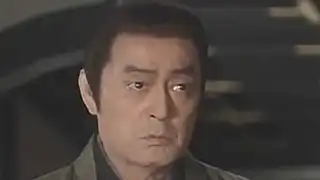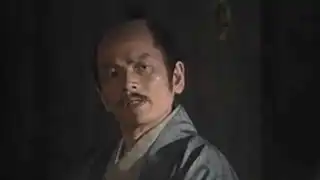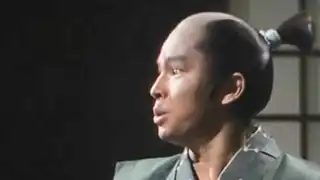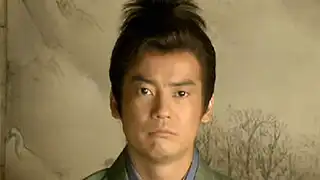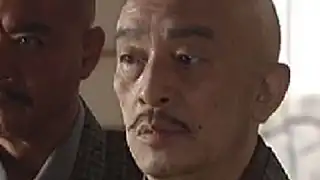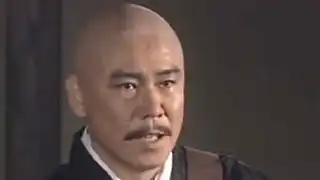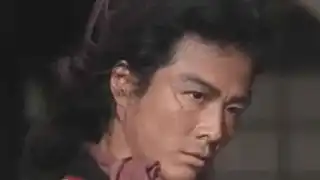 偉人
偉人石川五右衛門
いしかわ ごえもん(?-1594)
登場回数:2作
石川 五右衛門(いしかわ ごえもん、弘治4年〈1558年〉? - 文禄3年8月24日〈1594年10月8日〉、12月12日とも)は、安土桃山時代の盗賊の首長。文禄3年に捕えられ、京都三条河原で煎り殺された。見せしめとして、彼の親族も大人から生後間もない幼児に至るまで全員が極刑に処されている。 従来、その実在が疑問視されてきたが、イエズス会の宣教師の日記の中に、その人物の実在を思わせる記述が見つかっている。 江戸時代に創作材料として盛んに利用されたことで、高い知名度を得た。
登場回数:2作
石川 五右衛門(いしかわ ごえもん、弘治4年〈1558年〉? - 文禄3年8月24日〈1594年10月8日〉、12月12日とも)は、安土桃山時代の盗賊の首長。文禄3年に捕えられ、京都三条河原で煎り殺された。見せしめとして、彼の親族も大人から生後間もない幼児に至るまで全員が極刑に処されている。 従来、その実在が疑問視されてきたが、イエズス会の宣教師の日記の中に、その人物の実在を思わせる記述が見つかっている。 江戸時代に創作材料として盛んに利用されたことで、高い知名度を得た。