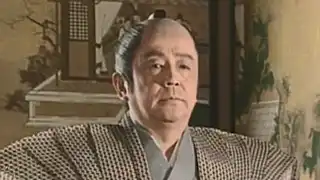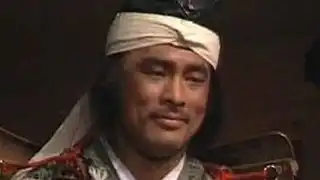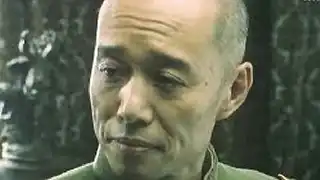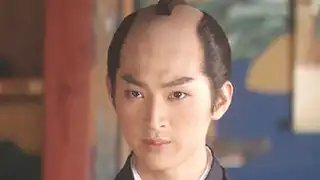 偉人
偉人徳川家茂
とくがわ いえもち(1846-1866)
登場回数:10作
別名:菊千代/徳川慶福
徳川 家茂(とくがわ いえもち)は、江戸幕府第14代将軍(在任:1859年 - 1866年)。初めは第12代将軍・徳川家慶の偏諱を受け、慶福(よしとみ)と名乗っていた。 実父・徳川斉順は家慶の異母弟で、家茂は第13代将軍・家定の従弟にあたる。将軍就任の前は御三家紀州藩第13代藩主であった。 徳川斉順(清水徳川家および紀州徳川家の当主)の嫡男であるが、父は家茂が生まれる前に薨去している。祖父は第11代将軍徳川家斉、祖母は妙操院。御台所は孝明天皇の皇妹・親子内親王(静寛院宮)。第13代将軍・徳川家定の後継者問題が持ち上がった際、家定の従弟にあたる慶福は徳川家一門の中で将軍家に最も近い血筋であることを根拠に、大老で譜代筆頭の彦根藩主井伊直弼ら南紀派の支持を受けて13歳で第14代将軍となった。
登場回数:10作
別名:菊千代/徳川慶福
徳川 家茂(とくがわ いえもち)は、江戸幕府第14代将軍(在任:1859年 - 1866年)。初めは第12代将軍・徳川家慶の偏諱を受け、慶福(よしとみ)と名乗っていた。 実父・徳川斉順は家慶の異母弟で、家茂は第13代将軍・家定の従弟にあたる。将軍就任の前は御三家紀州藩第13代藩主であった。 徳川斉順(清水徳川家および紀州徳川家の当主)の嫡男であるが、父は家茂が生まれる前に薨去している。祖父は第11代将軍徳川家斉、祖母は妙操院。御台所は孝明天皇の皇妹・親子内親王(静寛院宮)。第13代将軍・徳川家定の後継者問題が持ち上がった際、家定の従弟にあたる慶福は徳川家一門の中で将軍家に最も近い血筋であることを根拠に、大老で譜代筆頭の彦根藩主井伊直弼ら南紀派の支持を受けて13歳で第14代将軍となった。