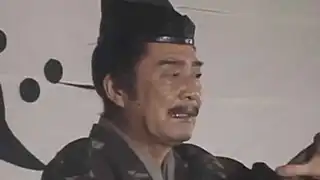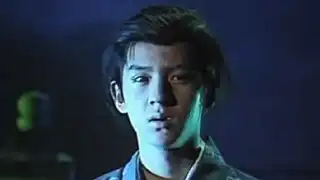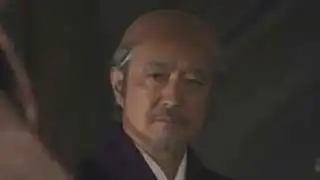 偉人
偉人安国寺恵瓊
あんこくじ えけい(1539-1600)
登場回数:9作
安国寺 恵瓊(あんこくじ えけい)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての臨済宗の僧で、武将および外交僧。道号(字)は瑶甫、法諱(諱)は恵瓊、号は一任斎または正慶。一般に広く知られる安国寺恵瓊の名は、住持した寺の名に由来する別名であり、禅僧としての名乗りは瑶甫 恵瓊(ようほ えけい)という。 毛利氏に仕える外交僧として豊臣(羽柴)秀吉との交渉窓口となり、豊臣政権においては秀吉からも知行を貰って大名に取り立てられたとするのが通説だが、異説もある。
登場回数:9作
安国寺 恵瓊(あんこくじ えけい)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての臨済宗の僧で、武将および外交僧。道号(字)は瑶甫、法諱(諱)は恵瓊、号は一任斎または正慶。一般に広く知られる安国寺恵瓊の名は、住持した寺の名に由来する別名であり、禅僧としての名乗りは瑶甫 恵瓊(ようほ えけい)という。 毛利氏に仕える外交僧として豊臣(羽柴)秀吉との交渉窓口となり、豊臣政権においては秀吉からも知行を貰って大名に取り立てられたとするのが通説だが、異説もある。