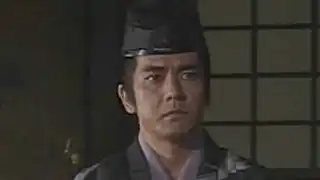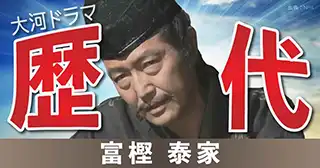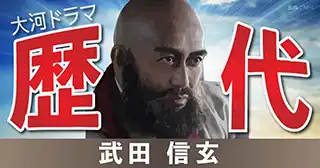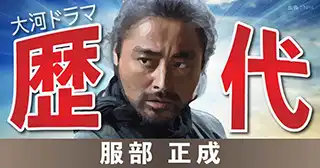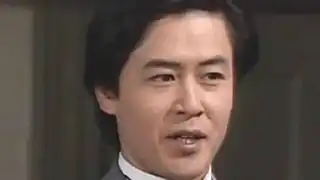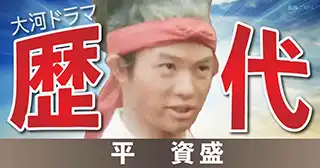偉人
偉人八木源之丞
やぎ げんのじょう(1814-1903)
登場回数:1作
八木 源之丞(やぎ げんのじょう、文化11年(1814年) - 明治36年(1903年)12月21日)は、江戸時代末期(幕末)の山城国葛野郡壬生村(現 京都府京都市中京区)の苗字帯刀を許された富裕郷士。八木家10代目当主。源之丞は通称。諱は応迅(まさはや)。本姓は日下部氏であることから朝臣としての正式な名のりは日下部応迅(くさかべの まさはや)。
登場回数:1作
八木 源之丞(やぎ げんのじょう、文化11年(1814年) - 明治36年(1903年)12月21日)は、江戸時代末期(幕末)の山城国葛野郡壬生村(現 京都府京都市中京区)の苗字帯刀を許された富裕郷士。八木家10代目当主。源之丞は通称。諱は応迅(まさはや)。本姓は日下部氏であることから朝臣としての正式な名のりは日下部応迅(くさかべの まさはや)。